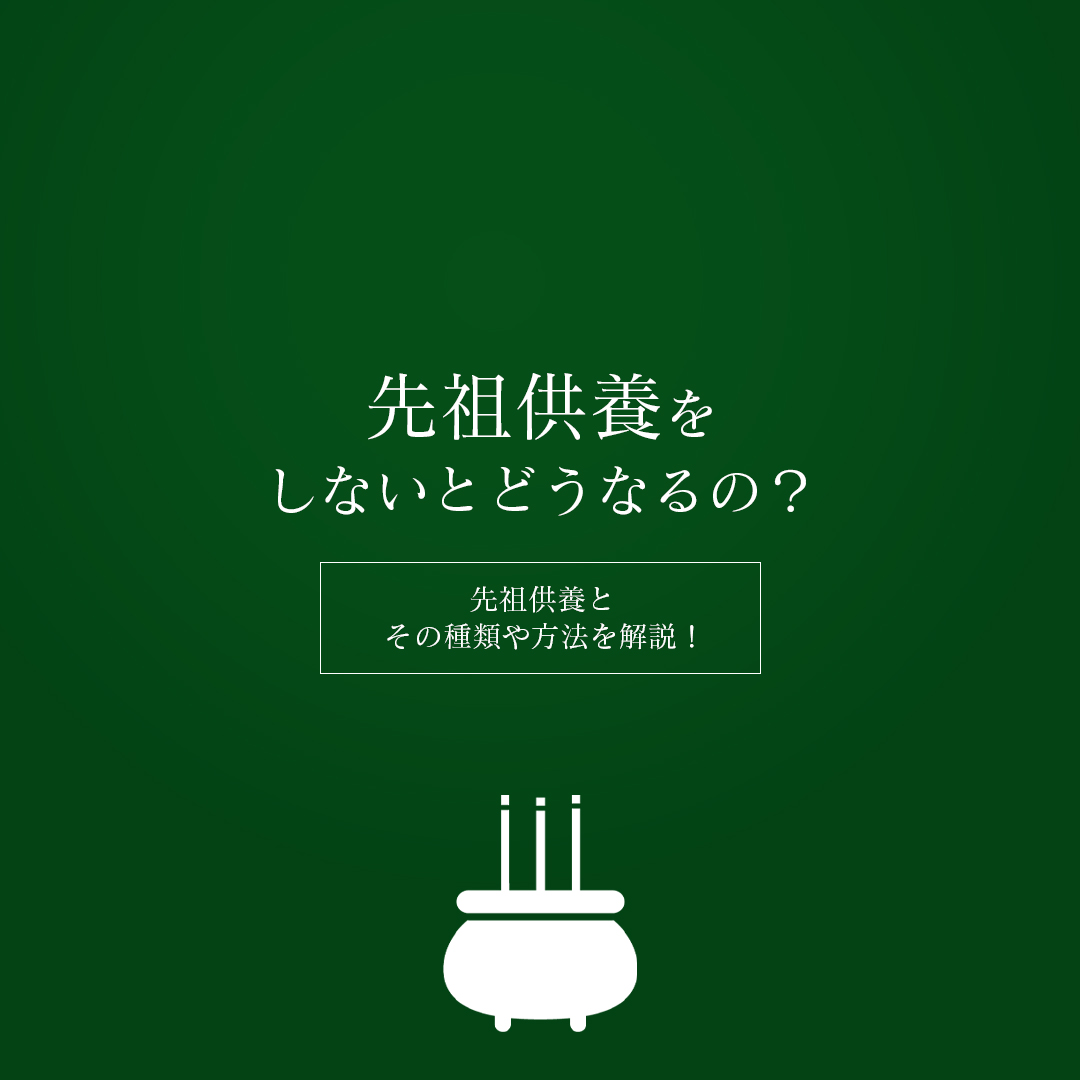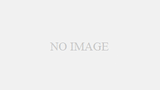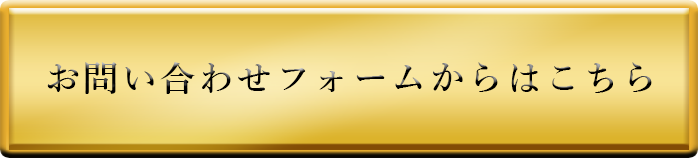先祖供養というものは、仏教での葬儀が一般的となっている日本で、長らく受け継がれて来た大切な務めの一つとなっています。
しかし、葬儀だけではなく様々な神事等に対してすらも関心が希薄になってきた現代では、先祖供養の正しい意味、先祖供養の本当の目的等を知らない人も多くなってきました。

そんな現代ということもあり、守るべきお墓や仏壇を所有している方は、先祖供養の方法や、先祖供養を行うタイミングなどが分からず悩むケースが数多くあります。
そこで今回は先祖供養が持つ意味や、具体的な先祖供養の方法、先祖供養をする際の注意点などに関して詳しく解説を行っていきます。
先祖供養とは?
先祖供養というものは、先祖の霊に対して感謝の気持ちを伝えることで、魂を鎮めて冥福を祈り、先祖が安心とともに成仏することを祈る仏教の儀式です。
まだ日本において“生贄”という、現代では悪習とされる風習があった頃は、人々は動物または生きている人間を活けにえとして神に捧げることで、起こり得る災いを回避するという儀式を行い、祈りを捧げていました。
この風習に対して、殺生を禁じている仏教が、生贄となった動物(または人間)の魂を手厚く供養することで、感謝の気持ちを伝えるようになったのが先祖供養の始まりとされています。

現在の先祖供養は、亡くなったご先祖様に対して読経や供物を捧げることで感謝の意を示し、功徳を捧げる行いが一般的となっています。
中には先祖供養を通すことで人は改めて命の大切さ、尊さ、ありがたみを感じ、自身の心の浄化を目的とする場合もあります。
その為、亡くなった先祖の霊というのは、現代に生きる人々のルーツといえる存在であるといえます。
先祖供養を行うことで、現代まで脈々と命を繋いできたことへの感謝を捧げ、今を生きているありがたみを実感し、感謝をします。
先祖供養で得られる物とは?
先祖供養というものは「先祖に対して行われる儀式」だと思われがちです。
しかし、先祖供養を行う人も得られるものがあるものなのです。
まずはその、先祖供養で得られるものとはなんなのかを解説いたします。
気持ちの安らぎを手に入れられる
先祖という言葉を聞くと、大半の人は「遥か昔の人」だと思うものです。
しかし、自身の祖父母や親といった自身の血縁となる近しい存在で、亡くなられてしまった人もその全てが先祖の霊なのです。

生前に関わりのあった人を思い浮かべつつ行う先祖供養は、その故人との楽しかった思い出や、共に過ごしたことで得られた感情など、そういったことを思い出して心が温かくなったりもします。
このような気持ちを共に捧げることで今を生きる人たちは、気持ちの安らぎとそして落ち着きを得られるものでもあります。
仏教においての徳を積むことができる
そもそも「徳」というものは、良い行いをすることで助け合うことを指します。
そして、それは誰かに強要されることで行うものではなく、自身の意思で自発的に動くことで得られるものとなっています。

先祖供養とは、自分の為ではなく、誰かの為に行うことで、「徳」を得られる=「徳」を積めるようになっています。
仏様や先祖霊の為に供物を捧げることで、僧侶によってお経をあげてもらい、お布施も合わせて感謝をすることで感謝をする行為が「徳」へと繋がります。
「徳」を積むということは、巡り巡って人と人同士の助け合いとなり、今を含め未来においても安定した生活へと繋げることが出来るようにもなります。
感謝の気持ちを持つことが出来る
先祖供養を行うことで、様々な出来事に対して「ありがたい」という感謝の気持ちを持つことが出来るようになります。

先祖が命を繋いでくれたことに対する感謝の気持ちだけではなく、仏様が見守ってくださっていることへの感謝、そしていま現在自身の生活を支えてくれている全ての物事へ対する感謝、このような様々な感謝の気持ちが生まれてきます。
この感謝の気持ち、所謂「ありがとう」という気持ちは人の心を温かくしてくれるものです。
先祖供養を通して、日常の生活では気付くことが難しい、感謝の気持ちを見つめなおしてみると、また何か新しい発見や気付きがあるかもしれません。
先祖供養の種類とは?
先祖供養というものは、どのような供養を行いたいかで先祖供養の方法も様々となっています。
その為、事前に先祖供養の種類を確認しておくことで、スムーズに物事を進めることが可能となります。
先祖供養の種類を解説いたしますので、先祖供養の種類確認の際にはぜひご参考にいただけますと幸いです。
追善供養という先祖供養
追善供養というのは、亡くなった方の魂が成仏することを目的とした先祖供養です。
亡くなった人に代わって、遺族の方や親族が法要を行うことで、その供養で得ることが出来た徳を、亡くなった方へと渡すことが出来ます。

そうすることで先祖の魂の徳が積まれていき、やがて成仏へと繋がります。
代表的な先祖供養としては「初七日」「四十九日」といった忌日法要、「一回忌」「三回忌」などのような年忌法要があります。
まさにこれらこそが追善供養のことです。
この他には、お墓参りや仏壇に対して手を合わせ拝むといった、日常的に出来る方法も追善供養とされています。
永代供養
永代供養というのは、お寺や霊園といった場所に故人の遺骨を預けて、遺族の代わりに管理者(僧侶など)が供養をする方法です。
特に近年では、少子高齢化の影響によって、お墓を継いで管理する者がいなくなってしまったり、供養への意識が希薄になってしまっている人が多くなってしまっています。

その為、永代供養で先祖の霊を供養するというケースがかなり増えてきました。
永代供養をお願いしておくことで、遺族に代わりお寺や寺院といった霊園が供養を先々もずっと続けてくれる為、弔い上げを迎えるようになるまでしっかりと安心いただけます。
先祖供養を行いたい、でもなかなか先祖供養をすることが出来ない。
そのような個人の様々な事情がある方には永代供養での先祖供養を検討してみてもいいのではないかと思います。
水子供養
水子供養というものは、この世に生まれることが出来ないままに亡くなってしまわれた胎児を供養することを指します。
この世に産まれ、生きることが出来なかったとしても、胎児には魂が宿っているものです。

冥福を祈ることで、あの世で幸せに過ごすことが出来るように供養を行い、そうすることでこの行いにも「徳」が生まれます。
そしてその「徳」は先述したように先祖供養へと繋がります。
一般的に水子の魂は、水子地蔵に導かれてあの世へと行くものであるとされています。
その為、水子供養を通じて先祖供養を行いたい場合は、水子地蔵が祀られている寺院で供養を行うと良いでしょう。
先祖供養の基本的な行い方
先祖供養における、基本的な先祖供養の方法はご存知でしょうか。
先祖供養の具体的な方法を知っておけば、いざという時に困ることも少なくなるのではないでしょうか。
そこで、先祖供養の基本的な方法を解説いたします。
忌日法要または年忌法要を行う
忌日法要または年忌法要というのは、故人が亡くなった日を1日目として考え、そこから日数を計算することで、節目とある日であったり年に合わせて行う法要のことを指します。

ひと昔前までであれば、初七日から始まって四十九日を迎えるまでの間に、7日ごとに法要が行われてきました。
しかし現在では、大きな法要だけを中心として行うケースが年々増えてきています。
例えば忌日法要の場合だと、初七日や四十九日だけを寺院にお願いして、他の日は自宅の祭壇や仏壇でお供え物をしたりといった方法があります。
年忌法要の場合だと一回忌、三回忌、十三回忌といった節目の時だけ大きな法要を行い、三十三回忌で永代供養を行うといった形となります。
個人の事情や周囲との兼ね合いもあるので、無理をせず自分に出来る範囲での年忌法要や忌日法要での先祖供養を行うことから始めてみてもいいでしょう。
お寺で行う先祖供養
どのような種類の供養であったとしても、お寺にお願いをすることで先祖供養を行ってもらうことは可能です。

忌日法要や年忌法要はもちろんのこと、永代供養や水子供養といった様々な先祖供養の相談をすることも可能となっています。
一番良いとされているのは、檀家となっているお寺に相談をすることも可能ではありますが、もしそういったことが難しい場合には周囲の人に相談したり、信頼できる寺院に供養をお願いしてみましょう。
自宅にある仏壇にお経をあげる
僧侶にお願いすることで自宅まで出向いてもらい、仏壇にお経をあげてもらうという方法もあります。

日常的に自分自身でお経をあげるということも出来ますが、その他の方法としてのお盆やお彼岸などといった節目ごとに僧侶にお経をあげてもらうというものがあるのです。
僧侶の方による説法を拝聴して、考えを深めていくことも功徳に繋がる行いですので、気になる人は僧侶の方へと一度相談して、ご自宅での読経を依頼してもいいでしょう。
卒塔婆を立てるという方法
卒塔婆というものは、供養を目的として立てる細長い板状のもののことです。
そもそも卒塔婆というものは、仏様の遺骨を納めたありがたい塔という意味を持っています。

卒塔婆を立てるだけでも、徳が積まれて供養になると考えられているので、それだけでも行う意味は大きくあります。
ただし、唯一、浄土真宗では卒塔婆での先祖供養を行っていません。
その為、ご自身の宗派を確認して依頼を行う先を決めるといいでしょう。
自分自身で行う先祖供養の方法
先祖供養というとどうしても「必ず、お寺や霊園にお願いをしなければいけない」と思われがちな場合が多々あります。
その場合、先祖供養を自分で行うとした場合はどのような方法があって、そして具体的な方法はどのようなものなのでしょうか。
こちらも解説いたしますので、ご参考にいただけると幸いです。
お仏壇に対して手を合わせる
毎日、お仏壇に手を合わせて、仏様と先祖の霊に挨拶を行うということも、日々の立派な供養に繋がります。

慌ただしく過ぎていく毎日の中でも、仏壇に手を合わせる時間をしっかりと毎日取って向き合うことで、無事に過ごせる感謝の気持ちだけではなく、喜びを感じられるのではないでしょうか。
もしまだ行っていないようであれば、一日一回で構わないので、仏壇の前に座って仏様や先祖へと感謝を伝える時間を取って、手を合わせるようにしてみましょう。
それが自宅で行える先祖供養の一つでもあり、基本でもあります。
お仏壇にお供えを行う
お仏壇へお供え物をすることで、そのお供え物が線香の香りと共にあの世へと運ばれていきます。
そうして、そのお供え物は仏様や先祖の霊に届けられると考えられています。

お仏壇へのお供え物は、仏飯やお茶といったものだけではなく、故人が生前に好きだった食べ物や飲み物でも大丈夫です。
生前まだ元気だった故人の姿を思い浮かべて、お仏壇へと手を合わせ、お供え物をすることで毎日の供養を続けてみましょう。
写真や遺品を飾って、それに対して手を合わせる
現代ではお仏壇を所有していない家庭がほとんどになりつつあります。
故人の写真であったり遺品を飾って、それに対して手を合わせれば、それだけでも大切な先祖供養となります。

忙しい日々の中でも、ふとした瞬間、ふとした時に目に入る位置へ故人の写真であったり遺品といった思い出の品を置くことで、大切な思い出と共に在りし日の故人の姿を思い出し、心が温かくなってくるでしょう。
お亡くなりになったことで、仏様の元にいるとされる故人の姿を忘れずに思い浮かべるというその行いが、そのまま先祖供養へと繋げることが可能です。
リビングのキャビネットや、窓辺であったり、小物を飾っているような飾り棚などでも結構です。
家族や自身の目につきやすい場所へと写真や遺品を飾ることで、いつでも故人を気にかけて手を合わせることが出来るようにしておきましょう。
それは先祖供養へと繋がります。
お墓参りによる先祖供養
当たり前ですがお墓というものには、先祖代々より故人の遺骨が埋葬されているものです。

その故人が眠るお墓へと足を運び、掃除をして綺麗にしお墓参りをするという行為は、先祖の霊や仏様が宿る場所を綺麗に保つという「徳」に繋がる先祖供養の行いでもあります。
そしてお墓参りの時期というのは、お盆やお彼岸や命日に限ったことではなく、ふとしたタイミングでなにか気になったり、お墓参りに行ってみようと思ったときでも構いません。
先祖と仏様に感謝をして手を合わせるようにしておきましょう。
仏教ではない先祖供養を行う方法
先祖供養は仏教がその始まりとされています。
しかし、仏教以外の宗教観で信仰をしている方も少なくはないでしょう。
では、もし仏教以外を信仰していて、先祖供養を行いたいと考えた場合、どのような方法がそこにはあるのでしょうか。
そこで、仏教ではない場合の先祖供養の方法を解説したいと思います。
迷った時や分からないときの参考にしていただけると幸いです。
神道における先祖供養とは?
神道での考え方では、亡くなった人の魂というものは、氏神様となって祖先の行く末を見守るものであるとされています。
したがって神道では、一般的な神棚とは別に故人の御霊を祀る場所を作る必要性があります。
そしてそれに対しては、お供え物をして手を合わせる必要もあります。
神道で先祖供養をする方法としては以下の通りとなっています。
霊璽を作る
霊璽というのは、仏教でいうところの位牌に相当する物です。
神道においては、人が亡くなると生前の名前から「霊号」と呼ばれる名前が付けられることとなります。
霊璽に故人の御霊を移して、そこで祀るようになっています。
霊璽そのものが神聖な存在となり、それを直接目に触れるようにすることは禁じられています。
したがって、霊璽を直接見てしまわないように布をかけたり、鏡の付いた錦の覆いを被せるというのが一般的な方法であるとされています。
霊璽を作成する際には、氏子となっている神社の神職に相談の上で用意をするようにしましょう。
そして祖霊社へ霊璽を祀る
そうして出来上がった霊璽は、祖霊社とされる神棚のような場所へと納めます。
神棚よりも低い位置へしつらえて祀るようになっています。
祖霊社には内扉と外扉が付いていて、霊璽は内扉の中へと納めて扉を閉めます。
そしてその外側に鏡を置いて、人の目に触れないようにします。
この祖霊社の外扉は開け放しておいても問題はありません。
お供え物として鏡の前へと「米」「塩」「水」「酒」「榊」を用意して、神棚と同じように「二礼・二拍手・一礼」してお参りをするようにしましょう。
キリスト教における先祖供養
キリスト教においては、日本に根付いた信仰とはまた違った考え方をするものとなっています。
その為、キリスト教の基本の考え方を学んだうえで、先祖供養に繋がる方法や行いをするようにしましょう。
キリスト教には供養という考えがない
キリスト教では、人の死というものは神の元へと帰る喜ばしいことであると考えられています。
その為、故人に対しての供養という概念は存在していません。

その代わりというわけではないのですが、折に触れ亡くなった故人を思い出すことで、故人の魂と神に対して感謝の気持ちを捧げるようになっています。
そういった理由から、供養という儀式そのものが存在していないのです。
故人への愛と神に対して、感謝の気持ちを常に持ち続ける。
そういった点に関していえば、仏教の供養と共通していると言えるでしょう。
家の中に家庭祭壇を作って神に祈る
あらたまった儀式というものはないのですが、より深く故人の魂や神に対して祈りを捧げたいと思う場合には、家庭祭壇を作るといった方法もあります。
リビングや広間などの一角へ、故人の写真や遺品、または清書や十字架といった小物類を配置します。
そして食事を摂る前であったり、眠る前、そして起床後に祈りを捧げることで、神と故人の魂に対して尊敬の念を表すようにする。
これが家庭祭壇を作って、神に祈るといった方法です。
先祖供養を行うにあたりよくある疑問
ここまで様々解説してまいりましたが、それでも先祖供養を行おうとした場合、多くの方が様々な疑問を抱えることとなるのではないでしょうか。
そこで、ここでは先祖供養でよく挙がる疑問点に対して、お答えしていきたいと思います。
先祖供養をしないと呪われるって本当?
人の中には先祖供養と呪いを関連付けて考えてしまう人も少なくはありません。
そもそも先祖供養の始まりとされてるのが「生贄とされた動物霊を供養する為の儀式」として始められたものなので、この説が転じた結果「供養をしないのであれば呪われる」という迷信が生まれたのだと考えられます。

その為、先祖供養をしたとしても「呪われたくないから…」といった気持ちだと、せっかくの先祖供養の行いが、感謝や敬愛の気持ちが伝わらず意味をなさないものとなってしまいます。
なので、先祖供養をしないと呪われるといったこともなく、逆に先祖供養をすることによって呪われる心配もありません。
なので、いつも今持ってくれていることに感謝して、その気持ちの上で先祖供養をするといいでしょう。
先祖供養は絶対にお寺にお願いしないと駄目なの?
先祖供養は前述のとおり、自宅でも自身で行うことが可能となっています。
その為、絶対にお寺にお願いする必要があるものではありません。
しかし、大きな忌日法要や年忌法要といった節目となる法要の際には、お寺にお願いをすることで遺族の気持ちも落ち着くだけではなく、法要に参列してくださる方々にも受け入れてもらいやすくはなるでしょう。
そういったこともある為、先祖供養の内容にもよりますが、状況に合わせて周囲と話し合いを行った上で、お寺にお願いをするべきかどうかを決めるのが最善でしょう。
先祖供養を行う必要があるのは仏教だけ?
先祖供養はその始まりもそうですが、基本的には仏教が発祥の儀式となっています。
しかし、世界中どの宗教においても「神へ感謝する」であったり「故人へ祈りを捧げる」といった所作は存在しています。
それは神道でもキリスト教でも思いという観点では一緒であると言えるでしょう。
その為、先祖供養とはされていなくても、信仰する宗教やその教え、そして考え方と状況に合わせて、それぞれに合った先祖供養の方法を考えましょう。
先祖供養にお金はかかるの?その相場は?
先祖供養の費用というものは、その行おうとする内容によって変わってくるため、一概にいくらといったことを言うことが出来ません。
例えば、忌日法要や年忌法要の場合だと、僧侶による読経をお願いすることでお布施として1万円~3万円ほどかかってきます。

それに加えて、お膳料やお車料までをも含めて考えると、3万円~5万円はかかってくることになるでしょう。
さらに永代供養を行おうとすれば、個人墓の場合は約40万円ほど、集合墓や合祀墓の場合であれば約10万円ほどが費用相場となっています。
そして僧侶による法要も、お寺によって大きく異なっている為、その場合の費用を算出するのは難しくなっています。
先祖供養の相場に関して気になる場合は、自身がどのような供養を行いたいか、そしてお寺や周囲に相談をしてみるといいでしょう。
先祖供養は開運に繋がるのか?
運気が悪い、良いことがない、そんなときには先祖供養をする、といった方も中にはいらっしゃいます。
しかしこれに関してはどちらとも言えない、というのが答えではないかと思います。

実際に先祖供養を行ったことで、「運気が上がった」「良いことがあった」と思える方もいれば、全然なにもないし変わらないという方も当然いらっしゃいます。
そもそも先祖供養というものは、自身の利益を求めて行うものではない為、先祖供養を行った結果、なんらかの見返りが自分にあると考えるものではないのです。
しかし、先祖供養を行うことで、気持ちが軽くなったというようなことはある為、そういった効果を以てして物事が良い方向へ動くことは十分にあります。
なので、開運の為ではなく純粋に先祖供養を行っておくといいでしょう。
先祖供養をするにあたっての注意点
先祖供養を行う場合には気を付けなければいけない点がいくつかあります。
代表的なものとしては「悪質な宗教勧誘」「願い事を叶えるといった甘言」「何もわからず言われるがまま」といったようなことです。
悪質な宗教勧誘に騙されないように注意!
先祖供養を食い物にするよな悪質な宗教勧誘もなかには存在しています。
明確な教えや、根拠、そして実績なども持ち合わせていないのに、なにかしらに先祖供養を絡めて悪質な勧誘をしてくる業者がいるのも事実です。

宗教や考え方、そして個々人の捉え方によって、最適な先祖供養を行うのがベストです。
その為、しっかりと相手の話を聞き、自身が納得の上で先祖供養を行うように心がけておきましょう。
願い事を叶える為ではない
先祖供養を行うことの本当の意味合いは、仏様と先祖の霊に対して感謝と敬愛を伝えるためです。
なにか自身の欲望や願望の為に、先祖供養を行うということは、先祖だけではなく仏様にも失礼に当たる行いです。
したがって、先祖供養を行う場合には、しっかりと先祖の為を思い、私利私欲を捨て去ってから臨むようにしておきましょう。
わからないまま物事を進めない
先祖供養の方法というものは、先祖供養の種類やその規模によってもやり方が変わってきてしまいます。
その為、細かい所で分からない点が出てくることもあります。
そのような場合には、どのような先祖供養を行いたいかということを明確にして、詳しいやり方などを寺院や周囲いに相談の上で、よりベストな先祖供養を行うようにしましょう。
まとめ
ここまで、先祖供養に関する内容を詳細に解説して参りました。
しかし、今回解説を行った内容というのは、その本質をみるとただの形骸化した儀式でしかないのです。
それはどういうことか?
要約すると、
「読経やお墓参りには、先祖供養としての大きな意味はない」
ということです。
体調が優れない、家が繫栄しない、人が寄り付かない、不幸ごとが立て続けに起こる。
そういった出来事の多くは、成仏できていない先祖の霊が影響を及ぼして、引き起こしている出来事なのです。
現代に生きる人のほとんどは、本当の先祖供養も、その先祖供養の意味も知らないまま生きています。
「なにか上手くいかない」そう思いつつも、どうすれば解決するのかも分からない。
そんな人が最後にたどり着くのが本当の先祖供養でもある、アトランティス協会の先祖供養なのです。
ただの形式的なものではなく、意味のある、意味を感じられる先祖供養をお約束いたします。
先祖供養のご相談はアトランティス協会までお願いいたします。